横浜FC戦と何が変わったのか?前半のベタ引きと、米本の存在
京都サンガ戦の感想で、グランパスの戦い方がかなり改善されたと書きました。
これ、良く書きすぎた気がしています。
横浜FC戦がひどすぎたので、ギャップに惑わされました。
中年の怪しい記憶力を頼りに、再度京都戦を振り返ります。
前半のベタ引きにより、コンパクトさと数的優位を保った
横浜FC戦では、コンパクト・数的優位という戦術を放棄した戦い方だった、と書きました。
一方、京都戦の特に前半は、FWまで自陣深くに引くことにより、全体のコンパクトさを維持しました。そのため、当然数的優位も生まれ、プレッシャーも密にかけられました。
また、FWもペナルティエリア10m手前くらいから、守備のプレスに参加したことで、穴だらけのプレスにはなりませんでした。
とはいえ、レベルが高い組織化されたプレス戦術ではありませんでした。京都のサポート・連動の動きが良く、やや部が悪かったですが、完全に崩しきれるほどの強さが京都になく、ゼロで抑えきりました。
初出場した米本の存在
もう一つ、大きかったのは、米本の存在でした。
とにかく、中盤で運動量豊富に厳しいデュエルで相手選手にプレッシャーをかけ続けました。
横浜FC戦にはなかった、彼の存在が、グランパス守備を再生させました。
また、攻撃面でも、決勝点につながる縦パスを通しています。
昨年、グランパスの中盤を支えた、レオ・シルバの代役として、特徴に違いはありますが、さらなる活躍が求められます。
名古屋の守備組織は改善されたのか?後半の不安定さがそれを否定している
京都戦の後半、あるいは先制後は、名古屋は高い位置からのプレッシャーをかけました。
上手くボールを奪う場面もありましたが、京都にかわされ攻め込まれる場面も目立ちました。
高い位置からのプレス戦術、まだまだ不十分です。
高い位置から追いかける前線、安全第一で下がるDFライン。組織は崩壊している?
FWが高い位置からプレッシャーをかける場合、当然DFラインを押し上げ、相手選手のパスコースを消す必要があります。
しかし、名古屋の場合は、DFラインが低いままで、相手選手のパスコースががら空きのことが多いです。
こうなると、当然プレスはかわされ、逆にピンチになりかねません。
少なくとも、ウイングバック、あるいはセンターバックで前に出られる選手は、最低でも中盤の守備に参加しないと、高い位置からのプレスは成立しないことが多いです。
この問題点を常に抱え続けているのが、名古屋グランパスだと思います。
レベルの高いプレス戦術が、備わっていない、それがグランパスです。
レベルの高い守備組織を根付かせるコーチスタッフが必要
プレスをかけるときの、この基本的な戦術を、選手に植え付けることができるコーチングスタッフが必要です。
この基本的戦術すら持たずに戦場に出ているのが、名古屋グランパスです。
Jリーグができてから、何年経ったのか。何度も言いますが、現代サッカーにおける必須の戦術です。
昨年、私が個人的に長谷川監督に期待したのは、この部分の組織的連動性の構築でした。
マスコミでは堅守の長谷川監督と書いてありましたので。
しかし、1年経ってもほとんど改善されず。
それが、横浜FC戦後の痛烈な3回のブログにつながりました。
横浜FC、京都サンガと、戦力的に差があるチームとの2連戦で勝利しました。しかし、チームの組織力では、明らかに対戦した2チームの方が上だったと感じます。
他チームの組織力が当然のごとくレベルアップしています。
にもかかわらず、名古屋の組織力は低く、戦力は他チームを圧倒する陣容でもないのが現状。
これからの名古屋には、レベルの高い組織的なサッカーを構築できる監督・コーチこそが、必要です。
過去の実績や、選手時代の実績は無意味です。
というか、これまでのチーム運営が、一体何を考え、何をしていたのか、疑問しか浮かびません。
またまたです
Colabo関連動画です。
東横インとどうも怪しい関係だったみたいです。
税金の使い方、やばすぎます。
最後まで読んでいただきありがとうございます。これからもたくさん記事を書いていくために、少しだけご協力ください。下の2つのバナーをクリック、もしくはポチッっとお願いします(名古屋グランパスの人気ブログの一覧画面が表示されます)。

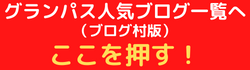

コメント