コンパクト・連動性に改善が感じられた守備
サガン鳥栖戦の、グランパスの守備面について、書いていきます。
まず、全体的な印象として、前節までよりも、組織的に連動し、FWからDFラインまでの距離もある程度コンパクトに保てていたと感じました。
そのため、厳しくデュエルでやり合う場面も増えたと感じました。
前節までは不安な点が多かったですが、一定水準の守備は構築できていた印象です。
以下で、内容を掘り下げていこうと思います。
高い位置からのプレスと連動した高いDFライン・パスコースを消す連動性
この試合の名古屋は、京都サンガ戦の前半のように、FWまで低い位置に下がることなく、比較的高い位置から積極的にプレスをかける守備でした。
そうなると、これまで問題になってきたのは、高い位置で追いかけるFW・MFと、低すぎる5バックとの距離でした。
しかし、この日はFWが前から追いかけた際は、5バックも高い位置を保ち、全体として一定以上のコンパクトさを保てていました。
オフサイドや、鳥栖のロングパスをセンターライン付近の高い位置でDFやWBが競るシーンがそれを象徴していました。
また、プレスをかける際の各選手のポジショニングも、相手パスコースを消す、あるいはパスを出されたらインターセプトできる・プレッシャーをかけられる位置取りが、ある程度できていた印象です。
前節までの、ドフリーの相手選手がちらほら見受けられる場面は少なかったと思います。
ひとまず、改善は見られたと感じました。
高いDFラインは、名古屋が主体的に作ったのか、鳥栖だったから実現したのか
しかし、この試合だけを見て、コンパクトさや高いDFラインが実践できるようになったと考えるのは、おそらく早計です。
それはなぜか?以下の仮説が成り立つからです。
それは、相手がサガン鳥栖だったから、名古屋もコンパクトさと高いDFラインを実践できたのではないか?
という仮説です。つまり、
- サガン鳥栖がコンパクトに3ラインを整えていたので、それに合わせて守った名古屋もコンパクトさを保てた
- サガン鳥栖がコンパクトな3ラインだったので、ボールが鳥栖陣内にあるときは鳥栖のFWの位置が低く、それに合わせて守った名古屋のDFラインも高い位置を保てた
という可能性も高いということです。
あくまで対戦相手次第であり、名古屋が主体的に実践したわけではなかった可能性があるのです。
そのため、引き続き次戦以降の内容を見て判断しなければいけません。
主体的にDFラインをコントロールし、主導権を握るチームへ
今回の考察については、以上となります。
全体的には、コンパクト、組織的な連動性、高いDFラインと、一定水準の組織的な守備はできていたと感じます。
この守備が、名古屋が主体的に実施できるかどうか、これからの試合でチェックしたいです。
そして、引き続き守備面の改善点として挙げられるのは、マッチレビューにも書いた、
- MFとWBが無駄に下がりすぎること
- ゴール前に全員が張り付きすぎること
の2つのポイントであり、長年の名古屋の大きな弱点となります。
ちなみに、改善されたとは言え、サガン鳥栖戦の守備は、最低限これくらいはできていないといけない、というレベルだったと思います。
もし本当に「堅守のグランパス」と謳うのであれば、ボールの取り所に相手がきたら、強烈なプレッシャーでボールを刈り取るくらいのパフォーマンスが必要だと思います。
ということで、サガン鳥栖戦の振り返り、守備編は以上となります。
水曜日のルヴァンカップは見ませんが、若手の活躍に期待しています。
最後まで読んでいただきありがとうございます。これからもたくさん記事を書いていくために、少しだけご協力ください。下の2つのバナーをクリック、もしくはポチッっとお願いします(名古屋グランパスの人気ブログの一覧画面が表示されます)。

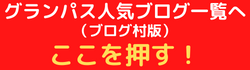

コメント