名古屋の決定機は防がれ、浦和は決め損ねた印象
ハイライトで決定機を見直します。
浦和最初の決定機:下がって対応した藤井
このシーンは、大久保のドリブルに藤井が下がって対応し、股抜きでかわされ、パス・シュートと持っていかれました。
最初に気になったのは、左サイドにボールが出た時点で中谷が安全を重視し過ぎて下がりすぎていたきがしました。
相手ゴール前からチェックに走っているので、オフサイド前提で前で取る守備で良かった気がします。
興梠が持った瞬間にオフサイドラインをひいていたところは良かったと思います。
毎回後ろに下がっては、全員のスタミナ消耗も激しくなります。
また、藤井については相手がうまかったのはありますが、極力下がらない守備ができるようになって欲しいです。森下もサポートに来ていたので、2人でボールを奪う守備が必要だったと感じます。
名古屋のチャンス:永井のシュート
この動画には入っていませんが、このシーンの前の森下のチェックがやや甘いのが気になってしまいました。酒井だと、あの距離からでも決定的なクロスがありえます(DAZNのハイライトに入ってました)。
永井のパスカットから、森下のパスを受け、ドリブルからのシュートはほぼ1人で決定機を作った良いプレーだと感じました。
マテウスのFKとCK
マテウスのFKは一発勝負。相手はプレッシャーを感じるでしょう。
稲垣のシュートは、再度、徹底的に練習して精度を上げるのもありかと感じます。
マテウスのサイドチェンジから森下のダイレクトシュート
マテウスのサイドチェンジが素晴らしかったです。全選手、これに近い、サイドチェンジ、アーリークロス、ロングフィードが出せるようになるのが理想です。中谷や野上などはいい感じのフィードが時々見られます。
森下はシュートチャンスが増えているので、シュート練習を増やした方がいいかもしれません。
名古屋:野上のロングフィードから、永井のトラップ、シュート
野上の鋭いロングフィードが永井につながり、うまいトラップからシュートへ。
浦和酒井がギリギリのスライディング、正面にGKと守りきられたシーン。
それぞれいいプレーでした。
浦和:右サイドからクロス、シュートは枠外へ
これが「ゴールへ流し込むだけ」の超決定機その一でした。
浦和としては、最後のクロスを無駄にバウンドさせてなければ流し込めていたと思います。
名古屋の守備は、一番最初、浦和右サイド一杯へボールを展開し、森下がチェックについているのに、永井がパスコースを切らなかったことがまず最初の問題でした。
そこから、酒井宏樹についた藤井の距離感の甘さ、振り切られた米本と、負の連鎖が続きました。
藤井はやはり距離をつめて相手を自由にプレーさせない守備がほしいです。代表で海外勢と戦うとすれば、今の距離感では通用しないと思われます。
名古屋:中盤のチェックから、こぼれ球のマテウスのシュート
マテウスのシュートは、左利きということで決めてほしかったところではあります。
相手GKが絶妙なポジショニングでした。
永井にパス、あるいは縦に抜けてからシュートorパスでも決まっていた気もします。
まあ、ストライカーなら仕方ないでしょう。
名古屋:ユンカーのシュート
このシーンも西川が抜群のポジショニングでした。いいキーパーですね。
浦和:自陣ゴール前からパスをつないでからの超決定機
これが2回めの、「流し込むだけ」のシーンです。
インサイドキックについて小言を
このシーンこそ、ラストパスのインサイドキックを無駄にバウンドさせたため、得点に至らなかったシーンです。試合を決める1点を取り損ねています。
「インサイドキックを無駄にバウンドさせない」ことの重要性を日本人はわかっていません。
古い代表選手で比較すると、中村憲剛のインサイドキックか、小野伸二のインサイドキックかの違いです。
インサイドキックは正しく蹴れば、バウンドしません。普段の練習からその意識を持って蹴っているか否かで、大事な場面でキックの質が分かれます。
「強いインサイドキックはバウンドしてもいい」というのは、日本人の間違った考え方です。
「正しくミートすれば、強く蹴ってもバウンドしない」が正解です。
ラストパスでは、特に精度が問題になります。蹴りやすいボールなら、浦和が得点していたでしょう。
名古屋の守備は問題なかったのか?
相手ボールになる瞬間、あるいは攻撃時の名古屋のDFラインの守備組織がやや崩れています。
相手選手がフリーになりすぎています。
ここ数試合、気になるのが、攻撃時の相手カウンターへの備え、という点で、特に守備組織の改善が必要かと感じます。
よりDFラインを上げ、オフサイドも利用しつつ、マンツーマン気味に相手パスコースを遮断しておきたいところです。
また、中谷が厳しくプレスをかけましたが、周りの選手がつめきれず。このあたりも組織的な守備の動きの向上が求められます。
基本的には、味方ゴールに近づける前にボールを奪うが理想です。
下がる守備では、強い相手を防ぎきれません。
川崎フロンターレ戦へ向けて:もう一段の組織力のレベルアップを
ハイライトでの見直しでしたが、守備組織についてはまだまだ改善の余地が多いと感じました。
開幕戦の悲惨な状況から、現状は最低限のレベルまでは向上したと感じます。
しかし、前節の新潟戦や、次節の川崎フロンターレ戦など、ポジショナルプレーが得意なチームに対抗するには、まだまだ不足しています。
- DFラインをコントロールして、オフサイドを利用しながら守備を構築する
- 組織的に連動してパスコースを切って、プレスをかける
- 対人守備では、1対1で距離をつめて、極力前に進ませない
- 攻撃時の相手カウンターへの事前対処
全選手が連動した、攻撃と守備。
基本的には、各選手が攻撃時も、守備時もベストなポジションを考えながら、ポジションチェンジを繰り返せば、それは自動的に成り立ちます。
その前提の上に、DFラインのコントロールによるオフサイドを利用した守備。
技術的には、パスの精度とスピードの向上。
ここまで問題なく構築されたら、私もフォーメーションを含めた戦術論の論議に参加することになると思います。
さらにその先に、プレッシングサッカーへ進むのか、あるいは、ポジショナルプレーやポゼッションに進むのかは、チームの方針、もしくは監督次第です。
チーム力向上のためには、ケガや疲労の蓄積がない範囲での、普段の練習の強度・質の高さは必須だと感じます。
川崎フロンターレ戦、熱い試合を期待します。
最後まで読んでいただきありがとうございます。これからもたくさん記事を書いていくために、少しだけご協力ください。下の2つのバナーをクリック、もしくはポチッっとお願いします(名古屋グランパスの人気ブログの一覧画面が表示されます)。

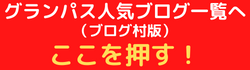

コメント